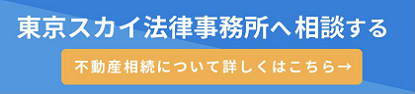不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
公開日: |更新日:
このページでは、収益物件として活用する不動産で相続税対策(節税対策)を行う方法や、不動産活用による相続税対策のリスクなどについてまとめています。
賃貸マンションなど収益物件として活用している不動産を相続する場合、物件の価値に関して時価と相続税評価額との間で差が生じるため、その差を活用して効果的な相続税対策(節税対策)に反映できる可能性があります。
ポイントは、一般的に収益物件の相続税評価額は、時価よりも低くなるという点です。
例えば、被相続人に預貯金で1億円の遺産があった場合、相続税評価額はそのまま1億円となり、それに応じた相続税を支払わなければなりません。
一方、不動産投資などのように、賃貸用マンションを第三者へ貸して賃料を得ている収益物件を相続する場合、不動産の価値は相続時の時価によって換算されず、あくまでも相続税評価額によって算出されます。その上、相続税評価額は通常、時価よりも低く設定されるため、結果として不動産を売却する場合の課税額よりも、不動産を相続する際の課税額の方が低くなるといったことになります。
不動産の相続税評価額が時価よりも低く設定されている理由は、不動産の所有権を得られる人に「権利の制限」があるからです。
通常の不動産売買の場合、不動産の所有権は物件を購入した人に認められます。しかし相続不動産の場合、不動産の所有権を認められるのはあくまでも相続人だけです。また、相続人が不動産を取得したとしても、賃貸物件として第三者へ貸している場合、借地借家法の適用によって借主の権利を無視することができません。
仮に、相続人が物件の売却や改修などを行いたいと考えても、先に入居者(借主)の同意を得なければならず、退去を求めるとしても、正当な立ち退き事由が認められなかったり、高額な立ち退き料や損害賠償を支払わなければならなかったりというケースもあるでしょう。
このような権利上の制限やリスクがあるからこそ、収益物件の相続に関しては、時価よりも相続税評価額が大幅に低くなっているのです。
収益物件を活用した不動産投資などを行っている場合、原則として不動産の所有者は最初に対象となる物件を取得しているはずです。また、被相続人が生前に不動産を購入していて、相続人がその所有権を引き継いだとしても、被相続人が住宅ローンなどを完済していなければ、借入金の残高が負の遺産として相続人へ引き継がれることになります。
さらに重要なポイントは、借入金の残高は相続税評価額に対してマイナス計上されるという点です。この流れは以下のような式として表せます。
収益物件の時価-(相続税評価額-借入金の残高)=期待される節税効果の範囲
つまり、不動産活用による相続税対策においては、借入金の残高であるマイナス分をどれだけ効果的に反映させられるかが、節税効果に影響するといえるでしょう。
だからといって高額な借入によって物件を購入してしまうと、相続税対策の効果が大きくなったとしても、ローンの支払いが困難になり、財政的に破綻してしまうリスクも生じます。そのため、積極的に借入金の残高による節税効果を活用しつつも、自分にとって無理を生じさせない、バランスを見極めることが肝心です。
不動産の相続に関しては、「小規模宅地等の特例」という税制上の優遇措置を活用できることも見逃せません。
小規模宅地等の特例とは、個人が相続などによって取得した不動産について、その物件が居住用や事業用として使用されていた場合に、一定の面積部分まで相続税評価額を減額するという制度です。
小規模宅地等の特例によって減額される割合は、物件の利用目的や面積によって変動しますが、例えば生前に被相続人が事業として、第三者へ物件を貸していたような場合、相続開始の直前における宅地等の利用区分が「被相続人等の貸付事業用の宅地等」となり、200m2を限度として50%が相続税評価額から減額されます。(令和2年4月1日現在法令等)
この結果、200m2以下の収益物件であれば、相続税評価額や借入金の残高という仕組みによってただでさえ時価よりも低くなっていた課税対象額が、さらに半額となり、相続税が大幅に減少するという成果を得られます。
なお、相続する不動産が被相続人の居住用に使われていた場合、限度面積を330m2として、80%まで減額されることも覚えておきましょう。
被相続人が住宅ローンへ加入して収益物件を購入している場合、被相続人はローン申請時に団体信用生命保険(団信)へ同時加入していることも多いでしょう。
団信とは、ローン契約者が債務を残して死亡したり所定の高度障害状態になったりした場合に、ローンの残高を保険会社が金融機関へ支払うための保険です。
通常の生命保険の場合、被相続人の死後、死亡保険金が保険会社から相続人へ支払われます。そのため、保険金は相続人の利益となり、相続税の課税対象となります。
一方の団信では、被相続人の死亡によって発生した保険金(ローン残債額)は、保険会社から金融機関へ支払われるため、相続人にお金が入ることはありません。つまり、団信によってローンの残債がゼロになったとしても、その分の相続税が相続人に発生することはありません。
ただし、団信はあくまでも住宅ローンの残債に対して支払われる保険金であり、その他の負債などについてカバーしてくれないため、団信に加入してさえいれば安心だという油断は危険です。
※参照元:長期固定金利住宅ローン フラット35|債務弁済される場合、債務弁済されない場合(https://www.flat35.com/danshin/shinki/bensai.html)
マンションやアパートを購入し、第三者へ貸して賃料を得る不動産投資は、長期的な収入源を確保できる資産運用として人気です。しかし、ただ相続税対策のみを目的として、きちんとした投資プランを構築せずに不動産投資へ手を出すと、キャッシュフローが破綻して、相続の前に不動産を手放さなければならなくなるリスクがあります。
また、相続時の借入金の残高を増やそうと、過度に高額な物件を購入し、高額の住宅ローンを組んだ結果、月々の支払額が高くなって、生活を圧迫してしまう恐れもあります。
不動産活用による相続税対策の節税効果は小さくありませんが、そもそも不動産投資で失敗すれば、結果的に大きな損をするリスクが高まります。そのため、不動産活用による相続税対策は、あくまでも「不動産活用が安定して成功している」という前提があってこそだと理解しておいてください。
賃貸割合とは、所有している物件がどれくらい賃貸契約で使用されているかという割合です。そして相続税評価額が時価よりも低くなる仕組みのポイントは、物件の借主の存在です。
つまり、借主が現れず空き室となっているような物件の場合、相続人(物件の所有者)の権利が制限されず、相続税評価額が時価へ近づいてしまうといった問題もあります。
逆に、例えばマンション一棟を使った不動産投資を行っているとして、満室の状態で相続することになれば、相続税評価額は時価よりも大幅に低くなると期待できるでしょう。
物件の空き室状況(賃貸割合)は相続税評価額へ影響するという点も、不動産投資の成功が相続税対策として重要になる理由の1つです。
相続人が複数いる場合、マンションやアパートのような不動産の相続について、遺産分割の方法を巡って相続人同士のトラブルに発展することも少なくありません。
特に、賃料収入による長期的な収益を期待できるような物件であれば、将来的な不動産の価値も考えて、遺産分割の方法や配分割合で揉めてしまう可能性が高まります。また、相続人によっては直ちに物件を売却・現金化して、現金を分け合いたいと考えることもあるでしょう。
不動産を相続することは、現金を相続する場合よりも節税効果を得やすい反面、相続人同士で揉めやすいといったデメリットもあります。
遺産分割のトラブルを解決するため、主となる相続人が不動産を相続する代わりに、他の相続人に対して現金を支払うといったケースは当然ながら想定されます。しかし、相続問題を協議している間もローンの返済は続くため、一気に現金を失うことでローンが返済困難に陥ったり、必要な修繕費をまかなえなかったりと、キャッシュフローの破綻を招くかも知れません。
また、被相続人が十分な現金を遺しておらず、相続人にも十分な預貯金がなければ、そもそも相続税を支払えずに物件を売却しなければならないことも想定されます。
不動産活用で相続税対策を考える場合、常に現金の余裕を持っておくことも大切です。
住宅ローンの加入時や団信への加入時に虚偽の申請を行っていた場合、被相続人が死亡しても団信が支払われず、想定していた税金の計算が狂う恐れがあります。
また、団信保険は自殺についても規定があり、ローン加入者が自殺したり故意に重度障害状態になったりした場合も、同様に保険金が支払われないため注意が必要です。
老後資金を確保したり、配偶者や子供へ資産を遺したりと、将来に備えて不動産活用を始める人は少なくありません。しかし、例えば高齢者が不動産投資を始めて、途中で認知症や、高度障害状態とは認められない病気にかかってしまい、不動産投資を維持できなくなるリスクがあります。
また、相続人が不動産投資を承継しても、物件を維持管理するための費用を捻出できず、負債が大きくなる恐れもあります。加えて固定資産税といった問題もあります。
不動産を活用して相続税対策に備える場合、相続する瞬間だけでなく、相続した人がどのように暮らしていくのかまで考えておくことが肝要です。
不動産活用による相続税対策を安全に実現しようと思えば、何よりも「不動産活用を安定させること」が欠かせません。また、相続人が複数いる場合、遺言書を用意しておくといった備えも重要です。
その他にも、認知症となった場合に備えて任意後見人契約の締結や、相続人となる配偶者や子供たちと生前にしっかり意識共有するなど、すべきことは多くあります。
相続関連の事柄は、相続人や、被相続人が個々に考えるべきことでなく、全員で共有しておくべき問題だと覚えておいてください。
Copyright © 遺産分割でもめたくない!不動産相続ガイド All Rights Reserved.