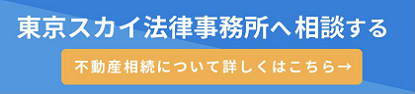不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
公開日: |更新日:
夫婦間の財産は共有財産として考えられていますが、場合によっては夫婦間の金品の授受や不動産の名義変更についても贈与税が発生する場合があります。このページでは、夫婦間の贈与税が生じるケースや対処法などについて解説していますので、ぜひ参考にしてください。
贈与とは現金や宝飾品、土地など資産価値のあるものを他人へ譲渡することであり、その金額や評価額に応じて発生するのが贈与税です。
贈与する現金の額や、贈った資産の価値が大きくなればなるほど贈与税の額も上がっていくため、適正な節税対策を考えなければ資産が大きく目減りする恐れもあります。
贈与税には基礎控除が設定されており、1月1日から12月31日までの1年間において、110万円までの贈与に関しては非課税となることもポイントです。言い換えれば、毎年110万円ずつの贈与であれば、贈与税を支払わずに財産を譲渡し続けることが可能です。
なお、贈与税の基礎控除はそれぞれ現金や資産を受け取る人に設定されているため、例えば5人の人へ110万円ずつを贈与するのであれば、合計550万円の現金を非課税で分配することができます。
共働きであっても、配偶者のどちらか一方だけに収入がある場合でも、夫婦として得た財産は基本的に夫婦の共有財産として認められます。特に一方の配偶者だけに収入がある場合は、収入のある方が扶養義務者となり、収入のない方は被扶養者となっているでしょう。この場合、扶養義務者には被扶養者の生活を支える義務が生じます。そのため、夫婦として家庭を支えるために必要なお金については、どちらが払っていたとしても原則として贈与税の対象になりませんし、扶養義務者が被扶養者の生活を支えるために支払っているお金についても贈与としては考えられません。
なお、夫婦として家庭を支えるために必要とされる費用としては、毎月の食費や家賃、光熱費といった生活費の他にも、子供の教育にかかる費用や同居の家族(扶養家族)の病院代など様々なものがあります。また、親から子供へ渡されるお小遣いや、夫から妻、あるいは妻から夫へ渡される誕生日の贈り物なども、常識の範囲内であれば贈与税の対象からは除外されます。
夫婦間の贈与であっても贈与税の基礎控除が反映されるため、年間110万円以下の現金や物品であれば常識の範囲外と考えられるお小遣い等であっても贈与税として課税されません。
ただし、贈与税の基礎控除は年間の贈与の総額で考えられるため、例えば40万円の現金を年に3回(合計120万円)渡した場合、超過分の10万円が贈与税の対象になることもあります。
夫婦間で贈与税が発生するケースとしては、単純に金品を授受する場合の他にも複数の例が考えられます。
たとえお小遣いであっても110万円を超える現金であったり、誕生日のプレゼントとして何百万円もする宝石類や車などを渡したりした場合、それは贈与税の対象として税務署が判断するかも知れません。また、妻の名義になる株式や金融商品といったものを夫が代わりに購入した場合、それは間接的な金銭の贈与として、贈与税の課税対象になることもあります。
どの程度の範囲を「常識」とするかは収入状況や生活レベルによっても変わるでしょうが、基本的に基礎控除の額(110万円)を超えるような金品や資産を譲渡する場合、夫婦間や親子間であっても贈与税の対象として判断されると考えておくことが無難です。
例えば夫が高齢になった夫婦では、夫の死後のことを考えて、夫の生前に自宅の所有者を妻へ名義変更しておくといったケースがあります。しかしこの場合、実質的に自宅という不動産を夫から妻へ譲渡したということになり、生前贈与と認定されることになるでしょう。そのため、自宅を受け取った妻には相応の贈与税の支払い義務が生じます。
また、相続時のゴタゴタを避けようと、最初から夫と妻の共有名義で不動産登記を行う場合もあるでしょう。とはいえその場合、不動産の取得にかかる費用の支払いは、所有権のバランスにもとづいて夫婦の双方が負担しなければなりません。
例えば夫と妻が2千万円の自宅について1対1の所有権を持っていながら、住宅の購入資金を夫だけが支払っていたり、ローンの返済を夫だけが行っていたりすれば、妻は自分の負担分1千万円に関して夫から支援されているという形になり、それも贈与の一種として判断されます。
不動産の名義変更や購入、所有権のバランスをどうするかは、贈与税についても意識しながら考えることが必要です。
例えば共働き世帯において、夫名義で住宅ローンを組んで購入し、夫が所有者となっている自宅があったとします。しかし夫の仕事の事情が変わって、途中から返済金の一部または全部を妻の収入から支払っているような場合、夫の債務を妻が肩代わりしたとして、贈与の一種になることがあります。
夫婦として互いに暮らしを支えていくことは民法においても義務づけられている重要な原則ですが、贈与税はあくまでも税法の観点から判断されるため、金額や条件によっては贈与税が発生する可能性があると覚えておくことが大切です。
場合によっては、それが贈与税の課税対象となるかどうか判断が分かれることもあります。
例えば、夫が妻に内緒で、妻名義の銀行口座へお金を振り込んでいたとします。この場合、妻自身が夫からお金を受け取っているという認識がなければ、贈与として認められない可能性があるでしょう。
夫と妻がそれぞれ個人の口座を持っている上で、夫婦の暮らしに使う生活費専用の銀行口座をどちらか一方の名義で持っているような場合も、事情がややこしくなります。
例えば上記の場合、妻名義の生活費専用口座へ夫が入金したとしても、それは妻への直接的な贈与でなく、あくまでも夫婦の生活費の一部を夫として負担していると考えられます。
ただし、金額の大きさによっては贈与とされる可能性もあり、ケースバイケースの判断が重要です。
離婚によって夫婦の共有財産を分配する財産分与は、原則として贈与税の対象外です。しかし、明らかに分配バランスに偏りがあるような場合や偽装離婚が疑われるような場合、税務署が贈与税の対象と判断するかも知れません。
夫婦間の不動産贈与や取得費用の贈与において、贈与税を回避したり税額を抑えたりする方法としては、配偶者控除を活用することが現実的です。
※以下の情報は令和2年4月1日現在の法令等にもとづいています。
婚姻期間が20年以上で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除額110万円とは別に最高2千万円(配偶者控除)を受けることができます。
つまり、他に現金などの贈与が行われていない場合、最高2,110万円までの自宅であれば夫婦間で所有権や取得費用を贈ったとしても、贈与税が発生しないということです。
不動産贈与における配偶者控除を活用するには、以下の適用要件の全てを満たさなければなりません。
なお、上記の適用要件を満たした上で、財産贈与を受けた日から10日以上が経過した戸籍謄本や登記事項証明書などの必要書類をそろえて、贈与税の申告をすることが必要です。
その他、同一の配偶者からの不動産贈与では一生に一度しか配偶者控除を活用できないことも重要です。
不動産贈与における配偶者控除を活用する場合、贈与税の対象額をきちんと算定した上で、必要な書類をそろえて期限内に手続きを適正に完了させなければなりません。
そのため、不動産問題に詳しい弁護士や司法書士へ相談して、きちんとしたサポートを受けることが賢明です。
Copyright © 遺産分割でもめたくない!不動産相続ガイド All Rights Reserved.