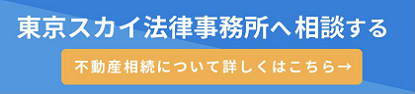不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
公開日: |更新日:
このページでは、不動産を相続した場合の土地活用について、相続人として注意すべき内容や上手に土地活用を行っていくためのポイントなどを解説しています。
親や配偶者から不動産を相続しても、生活拠点を他に持っている場合、相続した物件や土地で暮らすこともなく、持て余してしまうケースは珍しくありません。しかし、相続した不動産を放置していたり、そのまま所有しておいたりすることは、収益化によるメリットを得られないだけでなく、むしろ様々なデメリットやトラブルの種となります。
相続した住宅の使い道が見つからず、ひとまず空き家にしておくといった人は少なくありません。しかし現在は日本各地で空き家が増えて、建物の老朽化や放置による状態悪化が行政上の問題となっており、国や自治体も空き家対策を進めているといった事情があります。
そもそも、適正な管理者がおらず、ただ空き家として放置された物件は、人が暮らしている時よりも急速に劣化して周辺環境にとっても悪影響を及ぼすことが知られています。また、放火犯のターゲットにされるリスクなどもあり、空き家の解消は物件の所有者だけでなく、地域社会にとっても重要な課題です。
不動産を相続する場合、それが居住用や事業用に使用される物件であれば、税制上の優遇措置を受けることが可能です。また、固定資産税や都市計画税などに関しても、同様に居住用の物件に対する軽減措置などがあります。
一方、放置された空き家は管理不行き届きとして行政指導の対象になることがあり、さらに「特定空き家」の指定を受けると、税率が一気に上がってしまいます。
管理者や居住者のいない土地や物件は、やがて不法投棄の場所や、犯罪の温床になるため可能性が高まるので危険です。加えて、自分が所有する不動産で犯罪行為が発覚した場合、所有者責任を問われる可能性もあります。
不動産を所有していれば、毎年それに応じた固定資産税を支払わなければなりません。また、地域によっては都市計画税を課せられることもあるでしょう。
不動産は資産として考えられる反面、そもそも固定資産税などの税金がかかり、放置して状態が悪化すれば様々なリスクを発生させます。また、物件の種類によっては維持管理費が発生することもあり、相続した不動産を管理・活用せず放置することは、負債を抱え続けることと同じです。
もちろん、不動産を適切に維持管理するために必要なコストもあり、大切なのは常に利益と損失のバランスを考えることです。
土地活用の方法には様々なものがあり、その内容は相続した不動産の種類や状態によっても異なります。そのため、まずは不動産の性質や状態について正しく理解した上で、改めてどのような活用法が望ましいのか検討することが重要です。
すでに第三者へ貸していた物件であれば、そのまま借主に貸し続けることが最も簡単な土地活用の方法です。また、新たに入居者や借主を探してみても良いでしょう。
もちろん、被相続人が生前に自宅としていた住宅を、改めて賃貸物件として活用することも可能です。すでに入居者がいる物件であれば、特にコストをかけなくてもスムーズに収益化へつなげることができます。
土地については、駐車場やトランクルームとして貸し出すといった方法もあります。
物件を貸す場合も土地を使わせる場合も、個人で借主や利用者を見つけることが難しければ、不動産会社や駐車場経営のパートナー会社など専門業者に委託して、管理まで含めてプロに任せることも可能です。
その他、建築会社などと契約して、土地を資材置き場にするといった方法もあります。
現状では賃貸物件として価値が認められなさそうな物件であっても、リフォームやリノベーションによって新しい価値を与えることで、賃貸物件としての可能性が生まれるかも知れません。また、土地が余っている場合、そこへマンションやアパート、商業ビルなどを建築し、改めて賃貸物件として活用することもできます。
リフォームやリノベーションは、必ずしも居住用にすることが目的とは限らず、例えば倉庫にしたり商業店舗にしたりといった方向性もアイデアの1つです。
近年は、コインランドリーや飲食店、コンビニといった業界で、土地や物件のオーナーに対してフランチャイズ契約を提案している会社も増えており、新事業のチャンスとしても考えられます。
老朽化した建物を取り壊したり、不要な草木を伐採したりすることで、土地を更地にして活用法を考えることもできます。更地にすると住宅用地等の特例を受けられず、土地の税率が上がることになりますが、空き家を放置して指定空き家の指定を受けるよりはデメリットを抑えられる点が重要です。
また、更地の活用法としては、例えば太陽光発電システムを設置するといったものもあるでしょう。地域や条件によっては、更地にした土地を耕して現況農地を作り、農地転用を目指すといった選択肢もあります。
なお、農地転用が実現すれば、改めて税制上の優遇措置を受けられる可能性があります。ただし、農地転用には厳しい条件があり、適当な家庭菜園感覚では農地として認定されないので注意が必要です。
不動産の売却は、シンプルかつ速やかな現金化を目指せる方法の1つです。また、個人の住宅用に空き家を売却する場合、譲渡所得税の控除を受けられるといったメリットあります。
加えて、複数の相続人がいる場合、いっそ物件を現金化して遺産分割するといった結論に至るかも知れません。
どのような活用法を取るにしても、相続人全員の合意を得た上でなければ、後々にトラブルを引き起こすリスクが残ります。例えば、土地を売却したり、既存の建物を取り壊したりしてしまった場合、後になって遺産分割や土地活用の方法を変更したいと望んだとしても、手遅れとなってしまいます。
例えば、被相続人の住宅を、相続後にリフォームやリノベーションによって賃貸物件として再利用する場合、どれくらいのコストをかけることが適正なのか、地域の住宅ニーズや賃料相場も考えてバランスを試算しなければなりません。ましてや新しく物件を建てる場合は、初期費用の額も高くなるため、詳細な投資計画が不可欠です。
住宅用地・更地・農地なのかなど、土地の目的によって税率も変わります。固定資産税は毎年確実に発生するランニングコストであり、土地活用のプランニングをする上で欠かすことのできないポイントです。
不動産会社やパートナー会社を選ぶ際は、本当に信頼できる会社かどうかしっかり見極めることが重要です。また、特に相続関連の物件は取り扱いが難しい恐れもあり、親身になって考えながら、適切な活用法を提案してくれる会社を選ばなければなりません。
土地活用によって長期的な計画を立てる場合、不動産の価値は相続時点の評価額だけで判断できないこともあります。そのため、素人である相続人だけでは話がまとらまず、トラブルの火種が残りそうな時、相続問題や土地活用に詳しい弁護士など専門家に相談するといったことも必要です。
弁護士であれば、賃貸物件として第三者に不動産を貸す場合の、借地借家法に関連した注意点についてもアドバイスをくれるため、より一層に高度なプランニングを進められるようになります。
どんな土地活用を選択するにしても、まずは相続問題の解消が先であり、そのために被相続人が存命のうちに相談できる弁護士を見つけておくと良いでしょう。
Copyright © 遺産分割でもめたくない!不動産相続ガイド All Rights Reserved.