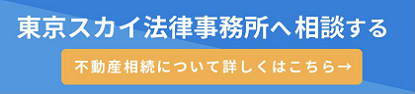不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
公開日: |更新日:
親族が亡くなり、不動産や戸建て住宅を相続した場合、各種手続きが必要です。「誰が相続するのか?」「何の手続きが必要なのか?」「複数相続人がいるときはどのような分割ができるのか?」などの疑問について、分かりやすくまとめました。
戸建て住宅を相続する場合、まずは名義を変更しなければなりません。相続した戸建て住宅を賃貸に出しや、売りに出すことも、名義変更が済んでいなければできません。書類を集めて手続きをしましょう。戸建て住宅を相続したときに、必要な手続きや流れをまとめました。
初めに決めるのが、誰が戸建て住宅を相続するのかを確定することです。戸建て住宅だけでなく、土地・家賃収入用の不動産や預金、車など相続財産を全て確認します。
などをチェックしましょう。相続対象となる法定相続人は、故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取得すれば確定できます。もし故人が再婚者の場合、前妻・前夫との間にいる子どもも法定相続人です。「初婚だと思っていたが、再婚だった」「再婚だったが子どもがいるとは聞いていない」など、トラブルにならないように、明確にしておきましょう。
故人が遺言書を残している場合は、遺言書にしたがって相続します。公正証書を作成している場合、公証人役場で調べましょう。故人が自筆で書いた遺言書は、開封しないで家庭裁判所へ持参します。ただし、故人が自筆で書いた遺言書であっても、公正証書となっていない場合、勝手に開封してしまうと無効になるので注意が必要です。
故人が借金を抱えていた場合、財産と同様に負債も相続されます。3ヶ月以内に相続放棄を家庭裁判所に申し立てれば、返済する必要はありません。ただし、相続放棄をすると、本来相続できる財産も放棄しなければいけないので、よく考えて申し立てをしましょう。
誰が何を相続するのかを決めたら、遺産分割協議書を作成します。遺言書があれば、内容に基づいて作成しましょう。遺産分割協議書は、相続する全員の署名・捺印が必要です。遺産が複数あり、相続対象人が多く揉めそうなときは、専門家に迷わず相談しましょう。遺産相続が原因となって、家族が疎遠になってしまうこともあります。
すべての財産を、誰が相続するのか決めなくてもかまいません。相続する財産が決まった順番から、相続人に移転できます。戸建て住宅や不動産など、名義変更の手続きが複雑なものから決めて、細かい財産は時間を置いて相続人を選定しもいいかもしれません。
遺産分割協議が完了後は、相続財産の名義を変更します。戸建て住宅を相続する場合、土地と建物の所有権移転登記を行います。各種書類を集めて、法務局に申請しましょう。申請先法務局は、最寄りではなく相続する戸建て住宅を管轄している法務局です。
居住地から遠い場合、郵送対応ができます。ただし、書類不備があった場合、修正やりとりをしていると名義変更までにかなりの時間がかかることも。できれば窓口に足を運んで、手続きすることをおすすめします。相続登記をする際に必要な書類は、以下のとおりです。
登記事項証明書は法務局で申請すると、発行してもらえます。他の書類は市役所で発行できるので、手続きをしましょう。本籍地が遠方にある場合、郵送してもらえますが、できるだけ早めに用意することがおすすめです。各市町村で郵送代や手続き手順などに違いがあり、時間を要する可能性があるためです。相続登記自体は期限がないため、いつでもできます。
しかし、長時間放棄していると不動産売却されたり相続人が亡くなって権利関係が変動したりなど、トラブルのもとにもなりかねません。相続が決まったら、すみやかに手続きをするのが望ましいでしょう。
また、名義変更をしたときは、登録免許税が発生します。
各種書類を集める際、発行するための費用がかかるため、事前にチェックしておきましょう。
相続登記を完了したら、相続税の申告・納付をします。戸建て住宅や不動産に限らず、遺産相続をした場合、相続税を支払わなければなりません。相続税の支払い期限は10ヶ月以内。戸建て住宅の相続税は、以下計算式で算出されます。
路線価は、国税庁のHPに記載してある「路線価図・評価倍率表」で確認しましょう。
相続税は基礎控除額が設定されています。控除された金額より遺産の総額が下回る場合、相続税は支払わなくてもOK。基礎控除は以下の計算式で算出されます。
他にも配偶者控除や未成年者控除など、種類がたくさんあるので該当するものがあるか調べましょう。
戸建て住宅は現金のように、均等に分けるのが難しい財産です。戸建て住宅の相続対象人が複数いる場合、4つの方法で分割できます。それぞれメリットやデメリットがあるため、自分がどの分割方法がベストなのか?よく考えてみましょう。
戸建て住宅を分割せず、1人が相続するパターンです。相続対象人の1人は戸建て住宅を、もう1人は現金など、それぞれ現物をまるごと相続します。戸建て住宅の相続権利を複数に分けないため、もし売却する際も同意を得る必要がありません。スムーズに手続きができます。不動産が戸建て住宅以外にもある場合、シンプルで揉めごとが起きにくい方法でしょう。
戸建て住宅を1人が相続し、他の相続人には同等価値の現金を渡すパターンです。故人と同居していた場合、引越しをしなくていいため、先の生活も困らないでしょう。ただし、戸建て住宅と同等価値の金銭を用意できる資金力が必要です。また、代償分割で渡す金銭は、遺産では賄えません。そのため、戸建て住宅を相続する人の財産から渡します。
戸建て住宅を売却し、得たお金を相続人で分けるパターンです。相続した家に住む予定がない&遠方に住んでいて、定期的な管理ができない場合、維持費を考慮して売却するのも1つの方法かもしれません。ただし、思い出の家がなくなってしまうため、悩む人もいるでしょう。また換価分割をする場合、相続人全員に譲渡所得税が課税されます。
分割せず、戸建て住宅を複数人で共有するパターンです。所有権を複数人でもつため、売却したり賃貸に出したりなど、何かするときは全員の合意が必要です。将来的な目線で考えるとリスクの高い相続とも言えるでしょう。できれば避けたい方法ですが、話をまとめやすく「とりあえず共有する」といった選択肢をとる人もいます。
戸建て住宅を分割する場合、まずは家がどのくらいの価値があるのかをリサーチしましょう。売却価格がある程度判明すれば、分割の選択肢が絞れます。遺産相続トラブルを回避できるでしょう。査定は基本的に無料で対応してもらえます。不動産会社に複数依頼して、相場を割り出してから分割方法を選ぶのが賢い選び方だといえるでしょう。
遺産相続は、通夜・葬儀が終わったあとから始まります。故人を偲ぶ間もなく、多数の手続きをしなければなりません。普段聞き慣れない言葉が多く、わからないことも多いでしょう。手続きや書類などに自信がない場合、弁護士に相談するのも1つの方法です。何にどのような手続きが必要なのか?代行できることもあります。親族間で揉めることなく、スムーズな手続きをしてくれるでしょう。
「仕事が忙しくて専念できない」「親族で話し合いがうまく進まない」という人にもおすすめです。初回は無料で相談に乗ってくれる弁護士もいます。まずは、無料相談に足を運んでみましょう。
Copyright © 遺産分割でもめたくない!不動産相続ガイド All Rights Reserved.